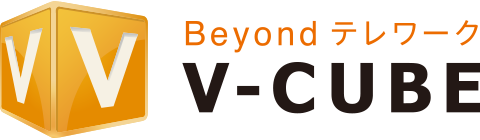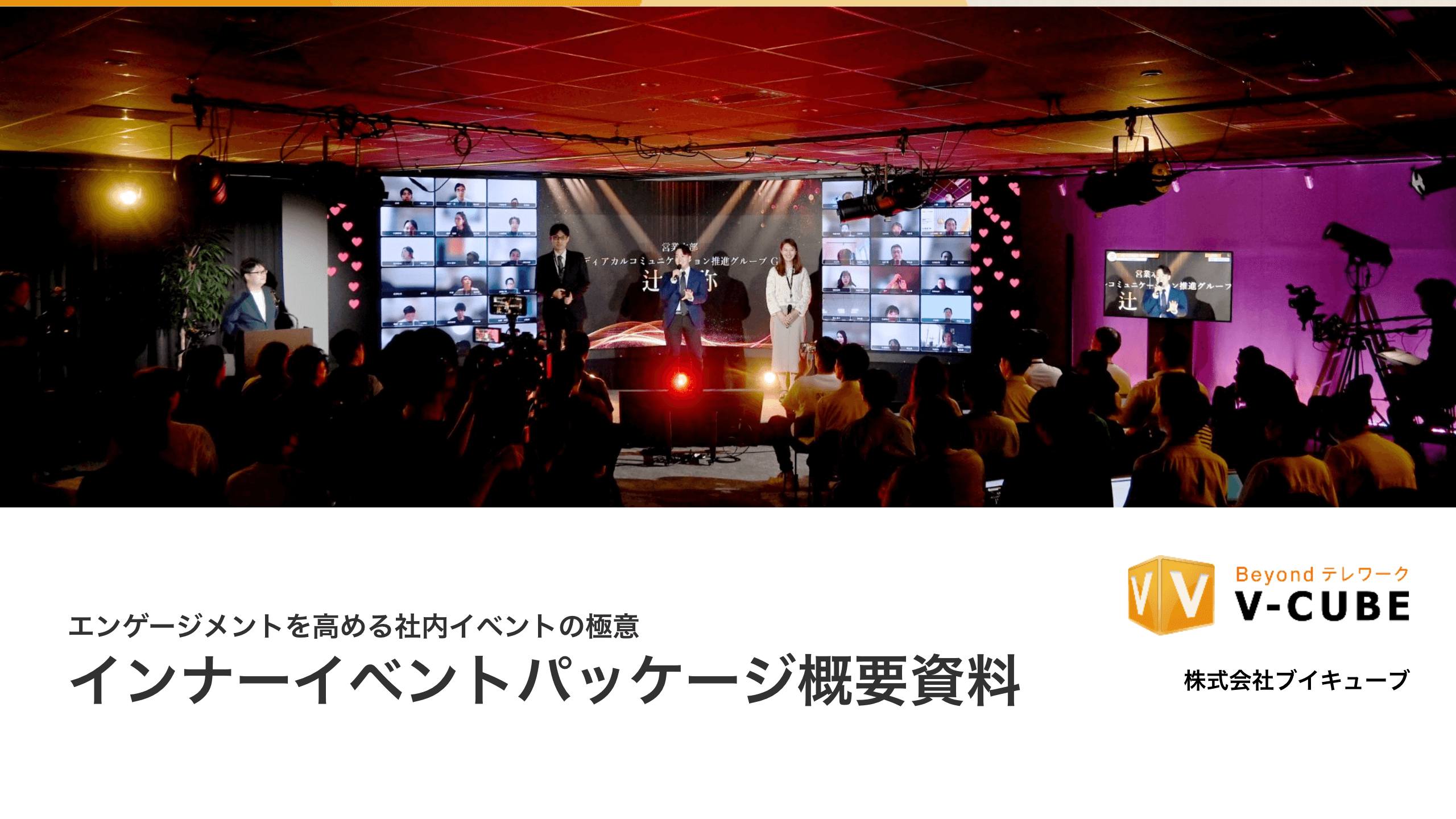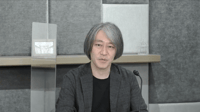2025年09月30日
社員の心を動かす社内イベントとは?エンゲージメントを高める企画術

目次
[非表示]社内イベントが注目されている背景
ここ数年で、働く環境は 様変わりしました。リモートワークの普及や出社・在宅を組み合わせた勤務スタイルの広がりに加え、人材の流動性の高まりや多様なキャリア志向も、社員同士のつながりを維持・強化する重要性を高めています。
勤務形態が多様化すると、以前のように日常的に顔を合わせて交流する機会が減るため、社員間のコミュニケーションが希薄になりやすくなることも。そのため、組織が意図的に「つながるきっかけ」を設けることが求められています。
社内イベントがもたらす4つのメリット
「社内イベント」は、単なる気分転換やレクリエーションとして捉えられがちですが、企業にとって大きなメリットをもたらします。主に以下の4つの効果が期待できます。
- 社員同士のコミュニケーション活性化
- 帰属意識の向上
- 企業理念やビジョンの浸透
- 離職防止や定着率の向上
ここではそれぞれについて詳しく解説していきます。
社員同士のコミュニケーション活性化
業務上のやりとりは仕事の話に偏りがちで、時間に追われる中では雑談の余裕はあまりありません。
しかし、社内イベントがあることで、日常の空気が変化が生まれます。例えば、部署を越えて 行うゲームや、気軽に参加できるワークショップなど、役職や部署の垣根を超えた活動は、普段話す機会のない社員同士の自然な会話につながります。
こうした交流を通じて、上司と部下はもちろん、他の部署の社員とも話す機会が生まれ、コミュニケーション不足の解消や信頼関係の構築につながります。結果として、日常業務における相談や情報共有が迅速かつ円滑になり、報告・連絡・相談のスピードが向上。チーム間の連携が強化され、業務ミスの低減や生産性向上、働きやすさの向上にも寄与します。
帰属意識の向上
社内イベントには、チームの一体感を生む力があります。目の前の業務に集中する日々の中では見えづらい、「自分はこの会社の一員なんだ」という実感。それを得るきっかけとして、社内イベントは 効果的です。
特に入社間もない社員にとっては、イベントを通じて先輩社員や他部署のメンバーとの接点を持つことで、組織文化や仕事の進め方を理解しやすくなり、会社の一員としての自覚を持ちやすくなるというメリットがあります。
企業理念やビジョンの浸透
企業の理念やビジョンは、言葉だけで伝えるのが難しいものです。パンフレットや社内ポータルに掲載するだけでは、社員が実際の業務とどう関係しているかを理解するのは難しいでしょう。
だからこそ、イベントを通じて「体験」として伝える工夫が重要です。経営層が直接話す機会を設けたり、チームごとに理念をテーマにしたセッションを行ったりすることで、社員は理念やビジョンを自分の仕事や判断に結びつけて考え、具体的な行動に反映しやすくなります。
離職防止や定着率の向上
人手不足や人材の流動化が進む中で、社員の離職防止や定着率の向上は多くの企業にとって重要な課題です。その解決の一手として、社内イベントが注目されています。
イベントによって職場の人間関係が良好になり、チームに居場所を感じられるようになると、社員は「もっとこの会社で働きたい」と感じやすくなります。また、感謝や成果を称えるようなイベントは、社員のモチベーションアップにもつながるでしょう。
目的別|社内イベントの種類と具体例

社内イベントは、その目的に応じてさまざまな種類があります。どんな目的で行うのかによって、企画の方向性や進め方は大きく変わってきます。ここでは、実際に多くの職場で行われている代表的な社内イベントと、それぞれの企画内容をご紹介します。
帰属意識の向上
社員が「自分はこの組織の一員である」という実感を持つことは、モチベーションやエンゲージメントを高めるうえで欠かせません。特にイベントを通じた経験は、社員同士のつながりや企業への誇りを醸成しやすい機会となります。ここでは、そうしたエンゲージメントの向上につながる代表的なイベントを4つご紹介します。
表彰式
1年間の努力を称える表彰式は、社員のモチベーションを高めるための効果的な取り組みです。受賞者にとってはもちろんのこと、その姿を見る他の社員にとっても「次は自分も」と思える前向きな刺激になります。例えば、「MVP賞」や「ベストチーム賞」に加えて、「挑戦賞」「努力賞」といったプロセスを評価するカテゴリを設けることで、より多くの社員が注目される機会を得られます。
周年記念イベント
創業からの節目を祝う周年行事は、企業のこれまでを振り返ると同時に、これからの未来を社員と共有するための大切な時間です。これまでの歩みを知ることで、「自分もこの歴史の一部なんだ」と感じられる社員も多く、その実感が企業への誇りや帰属意識へとつながっていきます。イベントでは、昔の写真を使ったスライド、創業者のトークセッション、過去のエピソード紹介などが効果的です。
企業理念やビジョンの浸透
企業が掲げる理念やビジョンを、社員一人ひとりにきちんと届け、共通の価値観として育てていく。それは、組織の一体感を高めるうえで欠かせない取り組みです。
ここでは、組織の土台をつくり、ビジョンを社員と共有するための代表的なイベントをご紹介します。
キックオフイベント
新年度やプロジェクトのスタートに合わせて実施されるキックオフは、組織の方向性を全員で共有するために重要なイベントです。企業全体のビジョンや方針を明確にしたうえで、各部署の目標や戦略を発表すると、社員一人ひとりの役割がより明確になります。
グループ単位でディスカッションを行うなど、参加型の企画を取り入れることで、一方通行にならない構成が可能です。前期の成果を振り返りつつ、新たな挑戦に向けたマインドを整える場として、チーム全体のモチベーション向上にもつながります。
全社総会
会社の方針や今後の方向性を全社員に伝えるために開かれる全社総会。この場は、単なる情報の伝達にとどまらず、社員のモチベーションを高め、組織としての「足並み」を揃える機会でもあります。
最近では、本社だけでなく支社や海外拠点にも同時中継されるようになり、オンラインやハイブリッド形式での開催も注目されています。離れた場所にいても、同じ空気感の中でメッセージを受け取れるという意味で、とても大切な仕組みです。
例えば、トップが未来について語るだけでなく、社員の表彰やトークセッションを織り交ぜることで、「自分もこの組織の一員なんだ」と実感できる構成にすることも。さらに、参加できなかった社員のために録画をアーカイブ化して共有すれば、時間や場所を問わず、全員が内容を受け取れます。
経営方針説明会
会社の現在地とこれからの方向性を、社員全員と共有するための経営方針説明会。この場を通じて、企業が「何を目指しているのか」がはっきりと伝わることで、現場との認識のズレを小さくできます。
説明会では、過去の実績を振り返りつつ、今期の目標や戦略をトップが自ら語るスタイルがよく見られます。中には、質疑応答やチャット形式でのやり取りを取り入れて、社員の声を拾い上げる仕組みを設けている企業もあり、社員へ前向きな刺激を与えらえれるよう工夫をしています。
リアル会場と配信を組み合わせる「ハイブリッド形式」なら、臨場感を残しながら参加のハードルも下げられます。一方的な発信だけでなく、双方向のやり取りが生まれる構成にすることで、「会社の言っていること」と「自分たちの実感」がつながっていくのです。
入社式・内定式
新しく会社に加わる社員にとって、入社式や内定式は最初に企業と向き合う場です。このときに感じた会社の雰囲気やメッセージが、今後の働き方や会社に対する姿勢に少なからず影響していきます。
近年は、全国に内定者がいることも多く、オンラインでの開催も取り入れられています。先輩社員からのビデオメッセージや、社長のライブスピーチなど、短い時間でも会社の方針や価値観、仕事の意義を具体的に伝えることが可能です。物理的な距離があっても、オンラインならではの工夫を取り入れることで、内定者が会社やチームの一員として自覚を持ちやすくなります。
新規事業コンテスト
アイデアをカタチにする場として、注目が集まっているのが新規事業コンテストです。社員が自由にビジネスプランを発案し、それをプレゼンテーションや企画書の形で発表するこの取り組みは、マーケティング、プレゼンテーション、財務など幅広いスキルが自然と磨かれるだけでなく、チームでの議論や工夫を通じて、協働力や問題解決力も向上します。
コンテストの企画次第ではありますが、内容が評価されれば、経営陣の目に留まり、実際の事業として動き出すことも。普段の仕事から少し離れて、新しい角度から自分の可能性を試せる貴重な機会です。チームで準備を進める中で生まれる議論や工夫も、大きな学びとなるでしょう。
また、組織全体のイノベーション創出や新規事業の機会拡大にも貢献できる取り組みです。
離職防止や定着率の向上
社員が安心して働き続けられる環境を整えることは、企業にとって大きな課題のひとつです。学びの機会や社会貢献活動を通じて「成長できる」「社会とつながっている」と感じられると、社員は自らの仕事に意味や価値を見出しやすくなります。その実感こそが、離職防止や定着率の向上につながる大切な要素です。ここでは、社員が前向きに働き続けられるための取り組みをご紹介します。
社内勉強会
社員同士が知識をシェアし合い、互いに学ぶ文化を育てる取り組みとして、社内勉強会があります。
これは、特定のスキルや知見を持つ社員が講師となって行うことが多く、実務に即した内容が扱われるのが特徴です。
例えば営業部門なら、効果的な提案資料の作り方や、信頼関係の築き方について。エンジニアなら、新しい開発ツールの活用法やプログラミングのコーディング手法についてと社内に眠っている生きた知識を共有が可能です。
スキルアップセミナー
専門的な知識や最新の業界トレンドを効率よく学ぶ機会として、多くの企業が取り入れているのがスキルアップセミナーです。外部から専門の講師を招くことが多く、幅広い内容を扱っています。
座学だけでなく、参加者同士で意見交換を行ったり、実践に近いワークを取り入れたりするケースも多く、ただ知識を得るだけにとどまりません。セミナー後に振り返りシートや実践レポートの提出を求めることで、学んだ内容を実際の業務に活かす流れも作りやすくなります。
地域社会貢献活動
地域との関係づくりは、企業がそこに「存在する意味」を実感するうえでも大切なテーマです。その第一歩として、地元での清掃活動や緑を育てる取り組み、災害ボランティアなどに参加する企業が増えてきました。
例えば、地元の小学校や福祉施設を訪問し、出張授業や職場見学を通じて「働く楽しさ」や「ものづくりの魅力」を子どもたちに伝えるケースもあります。こうした活動の中で、社員自身も「自分の仕事が、誰かの役に立っている」と実感するきっかけを得られるのです。
チャリティ・募金活動
もっと身近な形で社会貢献に参加できるのが、チャリティや募金を通じた活動です。一人ひとりが少しずつ行動することで、大きな力になるという感覚を得られる場でもあります。
最近では、災害時の緊急支援金を社員から募るほか、チャリティランやオンラインイベントと連動させたデジタル施策も広がってきました。自分の行動が誰かの助けにつながるという体験は、社員の中に「社会とのつながり」を感じさせてくれるものです。それは、やさしさや思いやりの文化を、組織の中に自然と根づかせる力にもなっていきます。
こうした取り組みを通じて、「自分の行動が会社の未来や社会の未来につながっている」と実感できれば、仕事への向き合い方にも変化が生まれるはずです。その企業姿勢は、社内だけでなく、取引先や社会からの信頼にもつながっていきます。
社員同士のコミュニケーションの活性化
通常の業務では、部署が違うだけで話す機会がないというケースも少なくありません。そうした垣根を取り払って、気軽に会話が生まれるきっかけをつくるのが、コミュニケーションを目的としたイベントです。単に楽しむだけでなく、信頼関係を築いたり、協力し合う土台を整えたりする意味でも大切な場となります。
忘新年会
年末の恒例行事である忘年会は、1年間の労をねぎらい、社員同士がリラックスした時間を共有できる貴重な機会です。多くの企業では、仕事納めのタイミングに合わせて開催されています。
形式としては、飲み会や食事会が一般的ですが、そこに簡単なゲームやクイズ、表彰などを加えることで、普段なかなか会話のない上司や、他部署のメンバーとも自然に交流が生まれやすく、社内の一体感が高まる場にもなります。また、労いという意味では会社から社員に対して感謝を伝える場でもあります。1年頑張ってくれた社員に対して、労いをする企業も増えています。
歓送迎会
新しく仲間に加わる社員を迎える「歓迎会」と、退職・異動にともなって送り出す「送別会」。これらを組み合わせた歓送迎会は、社内における大切な節目です。
寄せ書きやメッセージカード、思い出の写真を使ったスライドなど、少し手を加えるだけでも、印象に残るひとときを演出できます。そうした一工夫が、受け取る側にとって思い出に残る時間をつくるだけでなく、送る側にとっても、感謝や労いの気持ちを形にして伝えられる機会となり、コミュニケーションや信頼関係の強化につながります。
また、新入社員の歓迎会を通じて積極的に交流することで、新人社員の早期離職防止や職場へのスムーズな適応にもつながるでしょう。
運動会・スポーツ大会
社員同士がチームで協力しながら体を動かせるスポーツイベントは、コミュニケーションの促進や連携力の向上に役立つ社内イベントの1つです。業務では見られない一面が垣間見えるため、互いの理解を深める良い機会にもなるでしょう。
最近では、運動が苦手な人でも参加しやすいように、軽めの競技やミニゲームを中心とした構成にする企業が増えています。競技そのものよりも、チームで協力して目標を達成する経験が、日常業務における相談や情報共有を円滑にし、チーム内の連携強化や信頼関係の向上につながります。
社員旅行
社員旅行は、オフィスを離れて過ごす非日常の時間を通じて、社員同士の関係が深まりやすいイベントです。地元グルメを楽しんだり、チームでアクティビティに参加したりと、企画次第で交流の幅がさらに広がります。
宿泊をともなうことで、時間を気にせずゆっくりと会話できるのも、社員旅行ならではの特徴です。普段は業務の枠を越えて話せないような人とも、自然なつながりを持てる貴重な機会となります。
ファミリーデー
社員の家族を職場に招くファミリーデーは、企業と家庭とのつながりを強める取り組みとして注目されています。子ども向けのオフィスツアーや、仕事体験コーナー、社員紹介映像など、家族全員が楽しめる企画を準備しておくと、参加へのハードルが下がります。
さらに、家族が職場の雰囲気や社員の日常を理解することで、社員自身も自分の仕事や会社に対する誇りや帰属意識を再認識でき、エンゲージメントの向上につながるでしょう。また、家族同士や社員同士の交流を通じて、社内コミュニケーションの活性化にも寄与します。
社内イベント実施の7つのステップ
どんなに小さな社内イベントでも、丁寧な準備が成功の鍵です。ここでは、社内イベントをスムーズに実施するための基本的な7ステップを、時系列に沿って紹介していきます。

①イベントの目的を決める
最初に考えるべきなのは、「そもそも、なぜこのイベントを行うのか」という目的の部分です。コミュニケーションの活性化を目指すのか。企業理念を浸透させたいのか。あるいは、社員の成長を後押しするためなのか。この軸が定まらないまま企画を進めると、内容がぼやけ、最終的に「何のためだったのか分からないイベント」になってしまいます。目的を明確にすることで、企画全体に筋が通り、参加者へのメッセージも一貫性のあるものになります。その結果、設定した目的を効果的に達成できるイベントにすることが可能です。
②メンバーを選定する
目的が決まったら、それを形にしていくためのチームをつくります。イベントの規模にもよりますが、企画立案、運営管理、参加者への広報や案内など、役割を分けておくと安心です。
可能であれば、部署をまたいだメンバー構成にすると、さまざまな視点が加わり、企画内容にも深みが出てきます。
③予算・スケジュールを決める
次に、イベント全体にかかる予算を決め、準備に必要な期間や進行スケジュールを整理していきます。まずは、参加人数、会場、オンライン配信の有無などの大枠を押さえたうえで、残りの予算をどの部分に優先的に配分するかを検討します。 例えば、演出に力を入れるのか、食事を充実させるのか、講師を招くのかなどです。あらかじめ優先順位を共有しておくことで、限られた予算の中で設定した目的を効果的に達成しやすくなります。また、社内で必要な稟議や承認フローがある場合は、このタイミングで確認しておくと、後から慌てずに済みます。
④イベント内容を決めて告知する
イベントの目的や予算、日程が固まったら中身の企画に入ります。プログラムの構成を考え、どんな流れにするのか、どんな演出を加えるのかを具体的に詰めていきます。ここで意識したいのは、「参加者がイベントを通じてどのような変化や成果を得られるか」です。例えば、帰属意識が高まる、部署を超えたコミュニケーションが活発になる、新しい知識やスキルが身につくなど、具体的な効果を設計に反映させることが重要です。
プログラムが固まったら、開催に必要な場所の手配に取りかかります。リアル開催であれば、会場の広さや設備、当日の動線までしっかり確認しておくと安心です。
企画がまとまり、会場・配信手段が確定したら社内への告知を行います。社内ポータルやメール、ポスター、紹介動画など、複数の手段を組み合わせて、参加者の目に止まり、参加を促せる方法を選択しましょう。
⑤各種備品を手配する
オンラインやハイブリッド形式の場合は、配信ツールの選定や通信環境の確認、カメラなどの準備が必要です。また、外部業者に依頼する部分(司会、ケータリング、映像など)がある場合は、できるだけ早い段階で打ち合わせを始めておきましょう。イベントの備品は直前では準備できないものも多いため、余裕をもったスケジュールが重要です。
⑥イベントを開催・運営する
当日は、事前に立てた計画に沿って、スムーズに進行させることが求められるため、事前リハーサルを行い、進行手順や機材・配信確認、役割分担の確認を済ませておくことが重要です。 チーム内での役割分担や、緊急対応の動き方も事前に共有しておくことで、当日のトラブルを未然に防ぎ、万一の際も迅速に解決できます。運営時には、受付時の案内、質問対応のサポート、会場内の案内表示など、参加者が迷わず快適に過ごせるための具体的な配慮を行いましょう。また、イベントの様子を写真や動画で記録しておくと、後日報告や広報資料として活用することもできます。
⑦イベント後の振り返り・効果測定
イベントが終わったら、終了ではありません。必ず振り返りの時間を設けて、うまくいった点と課題点を明確にしておきましょう。参加者アンケートを通してリアルな声を集めることで、満足度や改善要望を把握しやすくなります。振り返りを次の企画に活かすことで、回を重ねるごとにイベントの質が高まっていきます。
社内イベントを成功させるポイント(オンライン・オフライン共通)
いくら準備を入念にしても、目的が達成できないイベントでは意味がありません。単に参加者に楽しんでもらうだけでなく、参加者の行動や意識に具体的な変化をもたらし、設定した目的を確実に実現することが成功のカギです。
ここでは、オンライン・オフラインどちらでも使える、成功のポイントを紹介します。
複数部署からメンバーを選出する
イベントの企画は、できるだけ多様な部署からメンバーを選出しましょう。特定の部署だけだと視点が偏りがちで、他の社員が共感しづらい内容になってしまうこともあります。
営業や総務、開発、管理部門など、異なる立場のメンバーが集まることで、アイデアに幅が出て、参加者のニーズにも応えやすくなります。また、運営チームそのものも 部署間の交流のきっかけになるでしょう。
特別感や意外性を盛り込む
社員が意欲を持って参加したくなるイベントにするためには、印象に残る仕掛けが必要です。例えば、経営陣の素顔を紹介するコーナーや、社員によるサプライズ演出があると、参加者の関心が高まり、より主体的にイベントに関わろうという気持ちが生まれます。
オンラインでも、リアルタイムの投票や抽選、クイズ企画など、インタラクティブな要素を取り入れると参加意欲が高まります。季節感やトレンドを反映させたテーマにすることで、毎回違った楽しみを感じてもらうこともできるでしょう。
イベント後の余韻が残る仕組みにする
イベントが終わったあとも、参加者の記憶に残るような工夫があると、全体の満足度が高まります。当日の写真や動画を社内ポータルやSNSに掲載したり、ダイジェスト映像を共有したりすることで、「あのイベントは楽しかったね」という会話が自然と生まれます。
特にオンラインイベントでは、リアルでの雑談が少ないため、あとから振り返れるコンテンツがコミュニケーションのきっかけになるのです。社内報で参加者のコメントや裏話を紹介するなど、小さな仕掛けでも次回への期待感につながります。
オンライン・ハイブリッド型で開催する場合のポイント
働き方が多様になる中で、社内イベントもオンラインやハイブリッド形式での実施が増えてきました。全国や海外にいる社員、自宅から参加する人など、場所を問わず関われるのが大きな魅力です。一方で、画面越しにどう一体感を生み出すかが課題にもなります。ここでは、オンライン・ハイブリッド型イベントを効果的に行うための3つのポイントを紹介します。
映像・音声のクオリティを高める
オンラインイベントでは、映像や音声のクオリティが体験全体の印象を左右します。映像が途切れたり、音が聞こえにくいだけで、集中力が途切れ、内容が伝わりにくくなってしまいます。
事前に通信環境や配信機材のテストは必須です。必要であれば、専門の業者に依頼するのも選択肢です。特にハイブリッド開催では、会場の臨場感と、オンラインの視認性・聞き取りやすさを両立させることが求められます。カメラの角度や切り替え、マイクの調整、照明の位置など、細かい部分まで丁寧に設計することで、伝わりやすい環境が整います。
双方向参加の仕組みを作る
オンラインイベントでは、見ているだけで終わってしまうことが多くなりがちです。そのため、参加者が「関わっている」と感じられる仕組みをつくることが重要です。リアルタイムでのチャット投稿や 投票、クイズ、グループディスカッション、ファンウォール、マルチアングルなど、双方向の仕掛けを入れることで、受け身から主体的な参加へと変わっていきます。
また、事前に質問を集めたり、イベント中に参加者の声を拾うような工夫も有効です。ハイブリッド開催の場合は、進行役がオンライン・会場の両方に目を向けて語りかけるだけでも、温度差が和らぎます。画面越しであっても、「自分もそこにいる」と感じられる演出が、全体の一体感を生み出します。
アーカイブ配信で後から見られるようにする
当日に参加できなかった社員にも機会を届ける手段として、アーカイブ配信が有効です。録画しておくことで、あとから好きなタイミングで視聴でき、拠点や勤務形態を問わず、情報の共有が可能になります。
経営層のメッセージや社内表彰の様子などは、何度も見返すことで理解が深まるコンテンツにもなります。単なる記録ではなく、ナレッジや社内資産として活かせるのもポイントです。さらに、再生データをもとに「どの場面が注目されたか」「どこで離脱があったか」を分析すれば、次回以降の改善にも役立ちます。
社内イベントの企画・運営はプロへ依頼するのもアリ!
社内イベントの準備や運営には、多くの時間と専門的なノウハウが必要です。特にオンラインやハイブリッド型での開催には、配信技術や演出の知識が求められます。
そこで、プロのイベント会社に依頼することも一つの選択肢です。クオリティの高い運営と演出により、参加者の満足度を高められるだけでなく、企画などの注力すべき内容に集中できます。中でも、ブイキューブのイベントコンサルティング「One イベント」は、イベント支援実績29,000件をもとに、社内イベントや表彰式、入社式、経営説明会など、さまざまなイベントを支援しています。
 ブイキューブのイベントコンサルティング「Oneイベント」導入事例はコチラ ▶
ブイキューブのイベントコンサルティング「Oneイベント」導入事例はコチラ ▶
まとめ
本記事では、社内イベントの種類やメリット、成功のポイント、そして実施までの流れをご紹介してきました。社員同士のコミュニケーション活性化やエンゲージメント向上、企業理念の浸透など、社内イベントは組織づくりに欠かせない重要な取り組みです。
とはいえ、イベントの企画・運営には多くの時間と専門的なノウハウが求められるのも事実です。オンライン・ハイブリッド型の開催が主流となる今こそ、経験豊富なプロのサポートを活用することで、より効果的で印象に残るイベントを実現できます。
ブイキューブでは、企画立案から配信・運営・演出までをワンストップで支援。 表彰式、入社式、全社会など、目的に応じた最適なイベント設計をお手伝いします。「自社だけでは不安」「もっと伝わるイベントにしたい」そんなときは、ぜひブイキューブにご相談ください。

執筆者ブイキューブ