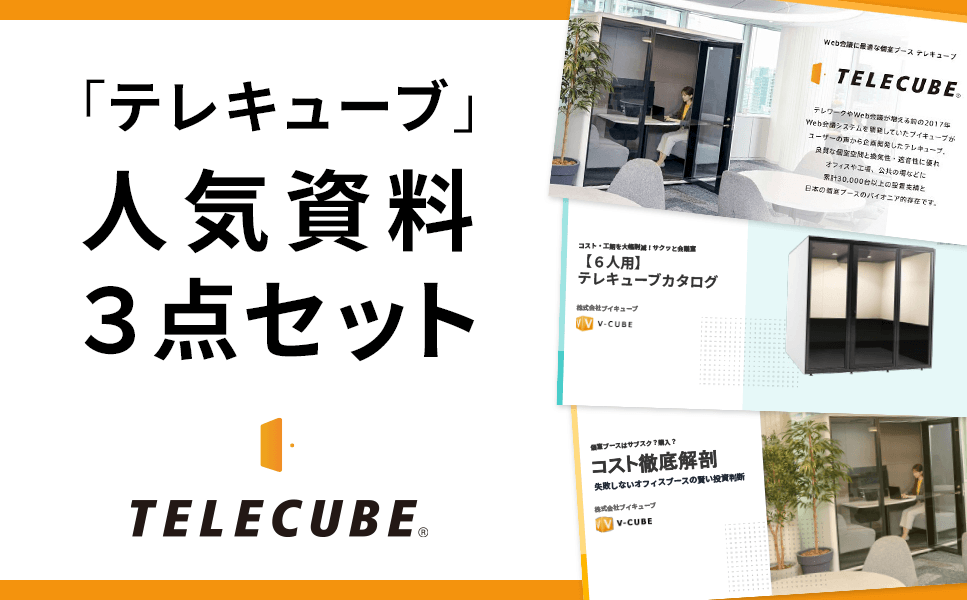2025年08月26日
【管理部門必見】ハイブリッドワークとは?メリットや成功のポイントを解説!
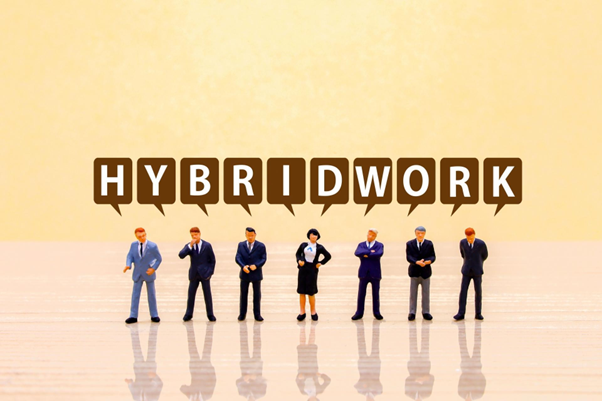
新型コロナウイルスの流行、いわゆる「コロナ禍」を機に注目度が高まったハイブリッドワークは、もはや一過性の働き方ではなくなり、企業の競争力を左右するレベルの重要な経営戦略のひとつとなっています。しかし、それを実際に導入する段階で、生産性向上や従業員間の連携など、具体的な課題に直面することも少なくありません。
本記事では、オンライン会議のプロフェッショナルである株式会社ブイキューブの多様な働き方の現場で培ったノウハウを生かして、ハイブリッドワークの基本的な仕組みから、導入によって得られるメリット、向いている企業の特徴、導入時に生じやすい問題や重視すべきポイントまで、要点を整理してわかりやすくお伝えします。
目次
[非表示]ハイブリッドワークとは?
ハイブリッドワークとは、出社とリモートワーク(在宅勤務やサテライトオフィスなど)を柔軟に組み合わせた働き方です。総務省による令和5年度(2023年度)のテレワーク人口実態調査では、雇用型テレワーカーのうち週1日以上テレワークを行っている割合が70%を超えており、週1〜4日のテレワークを通常の出社と組み合わせた勤務形態が広がっていることが明らかになりました。現在このような働き方は、企業の柔軟性や従業員の満足度向上を図る新しい手法として、多様な業界で定着しつつあるといえるでしょう。
ハイブリッドワークが注目されるようになった背景
ハイブリッドワークに注目が集まり、各企業が導入を進めたのは、コロナ禍を契機としてリモートワークが急速に普及したためです。総務省の調査によると、2021年に雇用型テレワーカーの割合がピークに達した後、2023年までには全国で24.8%とやや低下したことがわかります。

引用:令和5年度 テレワーク人口実態調査 -調査結果(概要) -
しかし、通常出社に週1〜4日のテレワークを組み合わせた勤務形態が定着し、週に少なくとも1日のテレワークを行う割合は約7割に上っています。都心部(東京圏)ではテレワークの普及率が特に高く、働き方の選択肢の幅が広がっている状況です。
 引用:令和5年度 テレワーク人口実態調査 -調査結果(概要) -
引用:令和5年度 テレワーク人口実態調査 -調査結果(概要) -
出社の頻度を抑えつつ柔軟に働きたいという、労働者側の意向が強くなっており、このようなニーズに合わせて、企業側にも生産性や従業員満足度の向上を目指す機運が高まったことが、ハイブリッドワークへの移行を後押ししています。
ハイブリッドワークのメリット

ハイブリッドワークは、働き方としての柔軟性が高く、働く側からの人気も高い魅力的なシステムです。しかし、実際に導入するとなると、本当に生産性や満足度が上がるのか不安に感じる方も少なくないでしょう。
ここでは、ハイブリッドワークを導入することで、期待できる以下5つのメリットを紹介していきます。
労働生産性の向上
テレワークやハイブリッドワークの導入は、通勤時間の削減によるストレスや疲労の軽減と、集中しやすい環境づくりに貢献します。財務省の調査によると、テレワークにより睡眠や自分の時間が増えたと回答する割合が多く、通勤時間分を有意義に活用する動きが広がっているといえるでしょう。
また、ハイブリッドワークにより世界全体では約60%、日本では約40%の社員が、生産性や仕事の質が上がったと回答している調査結果もあります。
ワークライフバランスの向上
ハイブリッドワークでは、在宅で働く日と出社する日を柔軟に使い分けられるため、家庭のための時間や自分自身の時間を確保しやすいのが利点です。通勤時間を省ける分、その時間を自由に使えるようになるため、ワークライフバランスの向上が期待できます。日々の生活に時間的余裕が生まれることで、働く人の精神的安定にもつながり、仕事への集中力や満足度の向上にも寄与します。
採用活動において有利になる
ハイブリッドワークを導入することで、企業の採用力を向上させるうえで大きな強みになります。昨今、求職者の多くが、柔軟な働き方が可能であるか否かを企業選びの重要な判断基準としており、特に若年層や子育て世代ではその傾向が顕著です。
勤務地に縛られない柔軟な制度を設けることで、遠隔地や時間的制約のある人材にもアプローチしやすく、結果として優秀な人材を確保できる可能性が広がるでしょう。また、働きやすさを実感しやすいため、従業員の定着率にもプラスの影響が期待できます。
オフィスに関するコストを削減できる
ハイブリッドワークを導入することで従業員の出社頻度が下がるため、オフィスに常駐する人の数が大幅に減ります。これにより、広いオフィススペースを維持する必要がなくなり、人件費の次に大きい経費とされている賃料や光熱費、備品関連費用などの固定費が削減可能です。
実際に、テレワークの普及を受けてオフィスの縮小や移転を検討する企業は増加傾向にあり、都心部の一等地から賃料が安い地域へオフィスを移転したり、フロア面積を縮小したりする動きが広がっています。
BCP対策にも効果的
BCPとは「Business Continuity Plan(事業継続計画)」の略で、災害や感染症の拡大などの緊急事態時でも、事業を停止せず継続できる体制を構築するための計画です。ハイブリッドワークを導入しておけば、出社が困難な状況でも、在宅勤務やサテライトオフィスで業務を継続できるため、BCPの実効性を向上させる手段として優れています。
内閣府の調査でも、BCP策定時に優先すべき要素として、テレワークやクラウド活用などが挙げられており、突発的なリスクへの対処法としても効果的です。
ハイブリッドワークが向いている企業とは

働き方の柔軟性を求める動きが強まる中で、ハイブリッドワークの導入を検討する企業が増えています。しかし、自社の業務特性や企業文化に合っているのか、制度を滞りなく運営できるのかなどの不安から、導入に踏み切れずにいるケースも少なくありません。
ここでは、ハイブリッドワーク導入が向いている企業の特徴を整理し、詳しく解説します。
場所に依存せずに業務が可能
ハイブリッドワークを円滑に進められる企業の特徴として、物理的な場所に業務が縛られないという点が挙げられます。そのため、クラウドやオンラインツールを活用することにより、自宅や外出先、サテライトオフィスなど、多様な勤務場所で支障なく効率的に働ける環境が整っている企業は、ハイブリッドワークとの相性が抜群です。
例えば、IT・システム開発会社、コンサルティングファーム、Webマーケティング会社、デザイン・クリエイティブ系企業、翻訳・ライティング業、オンライン教育事業者などが該当します。これらの業種は、パソコンとインターネット環境があれば業務の大部分を完結できるため、ハイブリッドワークを効果的に活用できるでしょう。
成果主義の評価体系
ハイブリッドワークと、成果を基準とした評価制度はよくマッチします。オフィス以外の場所で働く際には、勤務態度やプロセスを直接観察するのが難しいため、最終的な成果を重視する方が公平に評価可能であるからです。
テレワーク環境下での管理者の多くは、成果主義的な評価制度が適切であると判断しており、職務や目標をはっきりと定める人事制度の導入が進んでいます。成果主義の評価では、部署や個人ごとの成果指標を可視化し、数値や達成状況で評価する方法が効果的です。
成果主義をきちんと運用できる企業は、ハイブリッドワークと相性が良く、人材戦略の優位性も高まるでしょう。
従業員の働きやすさを重視している
社員の多様な働き方を支援する意識を持ち、働きやすさを重視している企業ほど、ハイブリッドワークとの親和性が高いといえます。柔軟な勤務時間や勤務場所を認め、心身の健康とワークライフバランスを支援する環境を構築している企業では、ずっと働き続けたいと感じる社員の比率も高くなる傾向があるでしょう。ハイブリッドワークを導入すれば、多様な社員が安心して働ける環境を構築可能です。
グローバルに人材を採用したい
国や地域を問わず、優秀な人材を幅広く採用したい企業にとって、ハイブリッドワークのシステムが非常に適しています。勤務地を柔軟に設定できる企業には地域や国を問わず応募者が集まるため、採用母集団の広がりが期待できるでしょう。
さらに、グローバル人材を育成・管理する体制が整っていれば、多様性を武器にグローバルな競争力を高められます。
【知っておきたい】ハイブリッドワーク導入に伴う課題

ハイブリッドワークは、働き方の柔軟性や作業効率の高さなど多くのメリットがある一方で、導入するだけではさまざまな課題に直面してしまうリスクもあります。制度として機能させるためには、現場で起こり得る課題や問題点、トラブルを事前に理解しておくことが重要です。
ここでは、ハイブリッドワークを導入するうえで注意すべき代表的な課題・問題点を紹介します。
社内コミュニケーションが不足しやすい
ハイブリッドワークを導入する場合は、コミュニケーションの希薄化に注意が必要です。出社日と在宅勤務日が混在することで対面機会が減り、情報共有やチームの一体感が損なわれる可能性があります。
コミュニケーション不足を解消するためには、定期的なオンライン雑談やフリーアドレスなどを実施することが大切です。ハイブリッドワークを運用する際には、コミュニケーション不足の課題を認識し、先回りして対策を準備しておきましょう。
勤怠や労働時間の管理がしにくい
在宅勤務では物理的な監視は難しいため、定時や残業・休憩時間などを正確に把握できず、従業員の勤怠や労働時間の管理がしにくくなる点に注意が必要です。対策としては、始業・終業の打刻をネットワークツールで行ったり、PCログインの記録を活用したりといった方法があります。ハイブリッドワークを導入する際には、制度設計と同時に、勤怠管理のシステム整備が不可欠です。
【重要】ハイブリッドワークを成功させるためのポイント
ハイブリッドワークの制度を導入したとしても、適切な運用体制と環境が整備されていなければ、期待した通りの成果を得ることは難しいでしょう。制度を効率よく機能させるためには、主に以下の4つのポイントを押さえておくことが重要です。
ここでは、それぞれ詳しく解説していきますのでハイブリッドワーク成功の参考にしてください。
- デジタルコミュニケーションツールを整備・導入する
- 最低限のルールを設定する
- 情報セキュリティを強化する
- 個室ブース(Web会議ブース)の設置
デジタルコミュニケーションツールを整備・導入する
リモート環境が主になるハイブリッドワークでは、ZoomやZoom Phoneなどのコミュニケーションツールを整備・導入し、従業員間の円滑な連携と安定した通話環境を構築することが非常に重要です。
リモートのみでコミュニケーションを取る環境では、情報共有や意思疎通にずれが生じやすいため、高品質なビデオ会議やビジネスチャットツールを導入しなければなりません。リモート環境に適したツールを選定し採用することで、勤務場所にかかわらず同じ業務情報にアクセスでき、タイムリーな対応が可能となるでしょう。
【導入社数3,400社以上の実績】Zoomの導入ならブイキューブにお任せ!
最低限のルールを設定する
ハイブリッドワークを機能させるためには、出社・在宅の基準や報告のルールを定め、統一的に運用することで混乱を防止することが重要です。特に、出社組とリモート組で情報格差が生じないよう、チャットやWeb会議、日報ツールなどを活用して、報告・連絡・相談のルールを整える必要があります。
例を挙げると、「毎週月曜日は全員出社日」「午前9時と午後5時に必ずチャットで稼働状況を報告」などのルールを設けると効果的でしょう。
これらのルールは現場の意見を聞きながら柔軟に調整し、定期的に見直すことが成功の鍵となります。
情報セキュリティを強化する
ハイブリッドワークに移行すると、オフィスの外で業務が行われることが常態化し、情報セキュリティのリスクが増加します。そのため、リモート環境でも安全に業務を行うため、VPNやクラウドサービスのアクセス制御、ID・パスワードの管理など、情報セキュリティの強化が不可欠です。
運用コストを削減するために、個人のプライベート端末を業務に使用するBYOD(Bring Your Own Device)を制度に組み込む企業もありますが、端末の紛失や業務外の経路から感染するマルウェアなど、情報セキュリティ上のリスクも多いため、導入には慎重な検討と徹底したルール制定が必要になるでしょう。
個室ブース(Web会議ブース)の設置
リモートワークが多くなる企業では、在宅勤務メンバーと出社しているメンバーとの円滑なコミュニケーションを支える個室ブース(Web会議ブース)の設置が効果的です。個室ブースを設置することにより、雑音や隣席の会話などで気が散ることなく業務に集中できるだけでなく、音漏れによる情報漏洩のリスクも軽減できます。
個室ブースには完全個室型や半個室型など、さまざまなバリエーションがあるため、自社の業務形態やセキュリティ対策に応じて、最適な型のブースを検討することが重要です。
個室ブースは高いと思っていませんか?サブスクなら月額47,800(税別)~
テレキューブ(TELECUBE)の導入でハイブリッドワークを成功に導く!
ハイブリッドワークを定着させるためには、自社の働く環境の整備が欠かせません。特に、出社時にストレスなく集中できる場所や、安心して静かな環境で在宅勤務メンバーとのWeb会議ができる環境などが確保されていることが重要です。また、働く環境としては、顧客との商談がWeb会議になっているケースも多い今では、出社時の会議で別の商談や社内の会話音声が入らないような防音かつ区切られた場所も必要になります。
このような課題を解決する手段として注目されているのが個室型ワークブースです。ここでは、ハイブリッドワーク導入を後押しするおすすめの個室ブースとして「テレキューブ(TELECUBE) 提供:株式会社ブイキューブ」の特徴とメリットを4つ紹介します。

高い遮音性や居住性でオンラインコミュニケーションに最適
テレキューブ(TELECUBE)は、高い遮音性能と居住性を兼ね備えた、完全個室型のワークブースです。周囲の雑音を遮断し、内部からの音漏れも防ぐ構造になっており、情報セキュリティが求められる会議や電話対応にも安心して使用できます。
ハイブリッドワークで多用されるZoomやZoom Phoneなどのビデオ通話・音声通話の際にも、集中して安全に作業できるため、業務効率やコミュニケーション品質の向上にも効果的です。
工事不要で簡単設置
テレキューブ(TELECUBE)は、従来の会議室と比較して圧倒的に低コストで設置できるという特長があります。一般的な会議室の新設の際には、「B工事」に該当する電気・内装などの工事が発生するため、期間も費用も膨らみがちです。一方で、テレキューブ(TELECUBE)は比較的工期が短く費用も安い「C工事」にて 設置できるため、通常時業務への影響も最小限に抑えつつ低コストで導入できることが大きな魅力です。
サブスクで設置できる
高品質の個室ブースを導入しようとしたとき、気になるのは価格ではないでしょうか?株式会社ブイキューブでは、サブスクリプションプランが用意されており、導入時のコストを軽減することができます。ハイブリッドワークで出社の比率が増えたときには会議室不足に悩むことになります。可変的に個室ブースを設置できるサブスクリプションプランでは、再び出社の比率が下がった場合でも、設置数を減らすという選択肢を簡単にとることができます。もちろん従来のような買い切りもできるため、ご状況に合わせてご相談いただくとよいでしょう。
個室ブースは高いと思っていませんか?サブスクなら月額47,800(税別)~
実績多数&信頼性が高い
テレキューブ(TELECUBE)は、数多くの大手企業・自治体・大学などに導入されており、信頼性と実績は業界でも高く評価されています。公共施設で見かけたことのある方も多いでしょう。オフィスや工場など、幅広い業種において累計30,000台以上の設置実績がある点も特長の1つです。品質・遮音性・安全性は各方面から高く評価されており、新たな働き方を支える選択肢として、多くの企業から選ばれています。
まとめ
ハイブリッドワークは、働き方の柔軟性と生産性を両立させられる新たなシステムとして、多くの企業で導入が進んでいます。オフィス維持のコスト削減や採用力の強化など多様なメリットが期待できる反面、社内コミュニケーションの不足や勤怠管理の難しさといった課題もあるため、導入の際には難しい局面にも遭遇するでしょう。
こうした課題を解決するための選択肢として「個室ブース」があります。工期とコストを抑えられ、遮音性や快適性に優れたテレキューブ(TELECUBE)は、リモートワークにおけるWeb会議や集中作業の質を高める選択肢として非常に有効です。ハイブリッドワーク導入を成功させたい企業は、ぜひ導入をご検討ください。

執筆者ブイキューブ