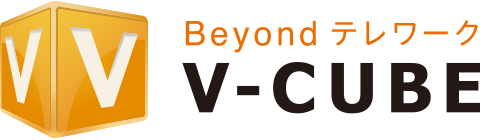ウェビナーとは?導入するメリット・デメリットとおすすめツールを紹介
2021.08.12

ウェビナーとは、Web上で開催されるセミナーのことです。
場所を問わずに労力やコストを軽減しながら数十名〜数百名規模で開催できるため、注目が集まっています。
新しい試みであるウェビナーに対して
- そもそもウェビナーとはどのようなものなのか
- ウェビナーのメリットとは
- 実際に行うにはどうしたら良いのか
などの疑問を持つ方も多いでしょう。
働く場所を選ばないテレワークが台頭してきた今、ウェビナーも普及していく可能性は大いに高く、理解を深めていくことが時代に対応していくのに必要不可欠です。
そこで本記事ではウェビナーとはどのようなものなのか、機能や配信方式、ウェビナー活用のメリット、注意点、導入事例をご紹介していきます。
- ウェビナー(Webセミナー・オンラインセミナー)とは?
- ウェビナーの6つのメリット
- ウェビナーの3つのデメリット
- ウェビナーを快適に行うためのWebシステムの機能5つ
- ウェビナーに必要な機能が備わるシステム
- V-CUBE セミナー・Zoomウェビナーを導入したウェビナー事例
- ウェビナーを成功させるためのポイント
- まとめ|開催目的に合わせてセミナー開催方法を決定しよう
はじめてのオンラインイベント開催ガイド

ウェビナーやオンライン説明会など、オンラインイベントを開催する際に必要な情報をまとめた資料です。ぜひお役立てください。
内容の一部をご紹介
- オンラインイベントを成功に導く事前準備ポイント
- 配信ツールの選び方
- プロが教える配信Tips
ウェビナー(Webセミナー・オンラインセミナー)とは?

ウェビナーとは「Web(ウェブ)」+「Seminar(セミナー)」を合わせた言葉です。動画配信システムとよく似ていますが、ライブ配信、録画配信、ライブ+録画配信など、多様な配信形態があります。
PCとインターネット環境がさえあれば、簡単に開催できます。
ウェビナーでは、参加者からのコメントや質問がリアルタイムに画面に表示されたり、それに対して出演者またはサポートスタッフがそれに返信したりといったインタラクティブ(双方向性のある)なコミュニケーションを取ることができます。
また使用するツールによって、1対1の説明会から、数百名の大規模セミナーの開催が可能であり、会場の規模にとらわれることもありません。
ウェビナーは、会社説明会、ツールの使い方講座、専門的な知識の講座などに用いられており、マーケティングの観点からも注目を集めています。
ウェビナーの配信方式:リアルタイム配信と録画配信
ウェビナーには、主にリアルタイム配信と録画配信2つの配信方式があります。
それぞれ配信形態や機能が異なるため、参加を見込めるユーザもそれに伴って変わってきます。
以下では2つの配信方法について詳しく解説していきます。
リアルタイム配信
リアルタイム配信は、決められた配信時間にセミナー参加者が動画を視聴する方法です。
参加者がコメントを書き込めるチャット欄を活用することで、双方向のコミュニケーションが可能です。説明会や講義形式のウェビナーの場合、参加者からの質問に答えることもできます。配信時間が決められていることから、よりリアルタイムに参加したいという関心の高いユーザーの参加が見込めます。
録画配信
動画配信は、あらかじめ録画された内容を配信し、セミナー参加者は後ほど録画された動画をストリーミングなどをし、自由なタイミングで視聴する方式です。オンデマンド配信とも呼ばれています。
録画配信であればいつでもどこからでも視聴できるため、リアルタイム配信の時間帯には都合がつかないユーザも参加でき、より多くの参加者の獲得に繋がるでしょう。また、同内容のセミナーを行う場合には録画配信を活用することによって、開催者側の手間やコストを削減することもできます。
ウェビナーの6つのメリット

ウェビナーには、従来のような会場開催型のセミナーにはない以下の5つのメリットがあります。
本章では各項目についてさらに詳しく解説をしていきます。
1.集客しやすい
従来の会場開催型のセミナーは、開催地に住んでいない人は物理的な距離によって参加のハードルが上がってしまいましたが、ウェビナーの場合はオンラインで開催され、参加者がPCやスマホなどから参加できるため、場所を選ばびません。
例えば会場開催型のセミナーでは開催地が東京の場合、物理的な距離によって遠方の顧客の集客が難しいという課題がありました。
しかし、ウェビナーであれば物理的な距離の問題が解決され、東京開催のセミナーにも地方の顧客が参加できるようになります。
つまり、参加者が抱くハードルの一つである場所の問題を解決することで、集客がしやすくなるのです。
場所を選ばずに参加できることは、ウェビナーの開催者と参加者の双方にとって大きなメリットになると言えるでしょう。
2.複雑な説明も簡単に共有できる
ウェビナーを行うWebツールによっては、画面共有機能やホワイトボード機能がついているものがあります。この機能を活用することで、資料共有をしながらホワイトボードに書き込んで説明でき、言葉や図だけでは説明しきれない複雑な情報も、補足しながら説明可能です。
またリアルタイム配信の場合には、疑問点をすぐにチャットで質問することもできます。
資料の共有やチャット機能などウェビナーには内容を理解しやすくする、様々な工夫がされていると言ってよいでしょう。
3.準備・運営の労力やコストを削減できる
ウェビナーは一般的な会場開催型のセミナーと異なり、会場の手配や受付、機材や資料の準備などの手間がかからないため、準備にかける労力や会場レンタル費用などのコストを押さえることができます。
少人数のセミナーであればオフィスの会議室を利用することもできますが、ある程度大人数での開催となるとそれなりの会場を用意する必要があります。そのためセミナーの規模が大きくなるほど、準備にかかる労力は大きくなるでしょう。
また、セミナーを行う会場費用はもちろんのこと、会場探しや見学・下見の人件費などもかかってきます。
一方、ウェビナーであればオフィスの会議室でツール上で配信準備をし、リアルタイムで配信・録画をするだけで簡単に開催ができます。会場を探すなどの事前準備の大きな手間をかけることもなく、会場のレンタル費用や人件費が大きくかかることもありません。
なお、一度開催したセミナーを動画として保存することで、二次利用もできます。会場開催型セミナーを何度も開催するよりもコストを抑えることができますし、現場メンバー・講師への負担も少なくできるでしょう。
4.ウェビナーの開催者側と参加者側が信頼関係を築きやすい
ウェビナーの機能により、参加者に開催側や講師のことを知ってもらいやすくなったり、コミュニケーションが生まれやすくなったりします。具体的には、ウェビナー上に顔やプロフィールを出しながら開催できたり、チャット機能を使って参加者が都度コメントや質問を手軽にできたりする機能を使うことで、信頼関係が築きやすくなるでしょう。
開催側から考えると、参加者の表情が見えない形式がほとんどのため、満足度の高い情報を提供できているか、不安に思われることもあるかもしれません。しかし、参加者からすると、大規模なリアルセミナーでは距離が遠かったり直接質問ができなかったりするなどの不安点が解決できるため、、比較的ウェビナーのほうが安心して参加してもらうことが可能でしょう
5.場合によっては確度の高いリードを獲得できる
ウェビナーの内容を細かくレベル分けして開催することで、参加者の確度をコントロールすることもできます。
具体的には、ウェビナーの申込フォームに氏名・所属企業・部署などの基本情報以外にも、ツール・サービスの検討・導入予定時期や、今回のウェビナーに興味を持ったポイントを細かく記入してもらうことで、確度の高いリード獲得にも繋がります。
さらにはMAツールと連携し、リードのナーチャリングに活かすことも可能です。
6.研修や営業用動画として活用できる
ウェビナーは自社で録画ができるので、前述したセミナーとしての利用だけでなく社員向けの研修でも再活用できます。
たとえば、金融機関が「資産運用についてのウェビナー」を開催し、後半で自社の投資商品のメリットを解説したケースで考えていきましょう。後半部分の録画を新入社員に見せることで、自社の商品のメリットや営業時の表現の仕方などの学びに役立てられます。
「ラーニングピラミッド」と呼ばれる学習定着率の研究では、文字を読むよりも動画を視聴する方が2倍ほど記憶に残りやすいと言われています。自社商品でもパンフレットを読み込むより、実際にプレゼンテーションの動画を視聴する方が商品・サービスの理解度を高めることができるでしょう。
また、動画を使うことで、営業ロープレを行う際に営業時の流れを1から考えるのではなく。実際にプレゼンテーションをしている様子を真似するところからスタートできます。「ラーニングピラミッド」では、文字を読むよりも人に教える方が9倍ほど記憶に残りやすいと言われています。プレゼンテーションしている動画の内容を真似して営業ロープレを行うことで、効率良く商品・サービスに関する研修を進められるでしょう。
商品説明や自社PRを含むようなウェビナーを開催するならば、録画しておいて社員教育にも役立てましょう。
ウェビナーの3つのデメリット
ウェビナーには多数のメリットがある一方で、以下のようなデメリットがあります。
本章では各項目についてさらに詳しく解説をしていきます。
1.視聴環境によっては快適に見られない
ウェビナーは、インターネット回線を利用して配信を行う仕組みです。そのため、どうしても視聴環境の影響を受けてしまうため、参加者のインターネット環境によっては、映像が途切れたり画像に乱れが生じたりします。開催者側がいかに設備投資をしたとしても、参加者の視聴環境を完璧にするのは難しいでしょう。
そのため、リアルタイム配信の場合でも、後ほど録画配信で見られるようにしておくことで、トラブル回避に繋がります。参加者の視聴環境によっては快適に見られないことに配慮して、配信方法を検討することがおすすめです。
2.参加者の満足度がわかりにくい
ウェビナーは会場型のセミナーと違い、参加者の顔を見ることができません。参加者が満足して聞いているのか、登壇者からわかりにくいのがデメリットです。
こうした問題は、ウェビナーシステムの機能を利用することで解決できます。多くのウェビナーシステムにはは参加者からのコメントや質問を募集できる機能があります。こうした機能を用いて、参加者からの質問に答えるなどの工夫をこらすことで、参加者の満足度を向上できます。
また、ウェビナーの開催後にはアンケートを実施して次のウェビナーに役立つ情報を集めることも重要です。
3.参加者の集中が途切れやすい
ウェビナーは自宅等で気軽に参加できる反面、参加者の集中力が途切れやすいものです。
会場型のセミナーであれば、途中で席を立つのは気が引けるでしょう。しかし、ウェビナーでは、他の参加者から見られていないので、簡単に席を立ったり他のサイトを見たりできてしまいます。
Faber Companyの調査では、ウェビナー参加者の6割が「何か他の業務をしながらウェビナーを視聴していた」というアンケート結果が出ています。
ウェビナーに集中してもらうためには、ユーザーに集中してもらうための工夫が必要です。リアルタイム配信であれば、参加型のウェビナーにしましょう。
参加者に質問をして回答してもらったり、参加者から質問を募って回答したりすることで、参加者が能動的になり集中しやすくなる効果が期待できます。また、録画配信であれば、参加者が飽きないように、編集やテロップを入れて見やすくしたり、問題を出して考えさせたりするのが効果的です。
ウェビナーを快適に行うためのWebシステムの機能5つ
ウェビナーに使えるオンラインミーティングシステムは、開催側と参加者双方が快適にウェビナーを実現するための機能が多数備わっています。以下、例としてあると便利な機能を5つ紹介します。
これからシステムを探す人や現在使用中のシステムがある方はぜひ参考にしてみてください。
1.チャット機能
チャット機能は、リアルタイム配信の際に、参加者が文字ベースで質問やコメントをすることができる機能です。
ウェビナーが行われている最中に浮かんだ疑問点を気軽に質問することができ、ウェビナー中でも開催側と気軽にコミュニケーションを取ることができます。
従来のセミナーの様な参加者が聞くだけの一方からの関りではなく双方向な関わり方を可能にするのが大きな特徴でしょう。
2.資料共有・メディア再生
資料共有機能は、ウェビナーが行われる画面上に資料やスライド、動画などを共有したり再生したりできる機能です。
従来のセミナーのように配布する手間なく資料を共有できます。
必要な資料を必要な場面ですぐに共有できるため非常に便利です。
3.ホワイトボード
ホワイトボードは画面上の資料にフリーハンドでテキストや図形の書き込みができる機能です。説明や解説をする際に口頭だけでは伝わりにくい部分を、資料に書き込みを行いながら解説できます。
参加者の理解度の向上に繋がるので、必要時にしっかりと使いこなしたい機能です。
4.録画・録音機能
ウェビナーならではの機能として録画・録音機能が挙げられます。セミナーを録音・録画することで手軽にセミナーの様子を共有でき、後からでも視聴できます。
ウェビナーの様子を開催者側が改めて確認し、ウェビナーの内容を改善したり、参加できなかった人へ共有したりするのに効果的です。
5.アンケート機能
アンケート機能は参加者全員に対してリアルタイムでアンケートを実施できるものです。
実際のセミナーのように参加者に対して質問をすることができます。
ウェビナー参加者の理解度を確認するのに活用でき、双方向の関りをするのに欠かせない機能です。
ウェビナーに必要な機能が備わるシステムを紹介
こちらでは、ウェビナーに必要な機能が備わる2つのサービスを提供しています。
前述した、チャット機能や資料共有機能などが備わっているサービスで、PCがあまり得意でない方でも利用しやすかったり、ウェビナーの準備から配信後までフォローしてくれたりするものを選んでいます。
ウェビナーを開催できるサービスをご検討の方はぜひ参考にしてみてください。
1)V-CUBE セミナー

出典:V-CUBE セミナー
弊社ブイキューブが提供しているV-CUBE セミナーは、ウェビナーに必要な以下の機能を備えています。
- チャット機能
- 資料共有機能
- ホワイトボード機能
- 録画・録音機能
- アンケート機能
などの機能が備えられているウェビナーツールです。
リアルタイムでのライブ配信機能と参加者がいつでもウェビナー動画を視聴できるオンデマンド配信機能のどちらも備えており、参加者の希望に応じて配信スタイルを変えることができます。
また参加者は専用のアプリケーションをインストールする必要はありません。面倒な操作はいらず、ご利用のブラウザから簡単にウェビナーに参加できます。
開催者にも参加者にも簡単に扱うことができるのがV-CUBE セミナーの大きな魅力でしょう。
さらに詳しくV-CUBE セミナーについて知りたい方はこちらも合わせてご覧ください。
2)Zoomウェビナー

Zoomウェビナーは、Zoomミーティングの有料プランを利用している方向けのオプションサービスです。ウェビナーを円滑に進めることができる以下のような機能が備えています。
- チャット・Q&A機能
- アンケート機能
- 録画機能
- 遠隔地から登壇できるパネリスト機能
- 申し込みページ作成機能
- YouTubeなどとの連携機能
Zoomウェビナーでは、「パネリスト」を指定することで、遠隔参加で登壇可能です。同じ場所に集まらなくても合同でウェビナーを開催できます。
また、申し込みページやアンケートの作成、YouTube・Facebookなどでのライブ配信対応など、集客から配信後まで、ウェビナーの運営を円滑にすすめるための機能を備えています。
Web会議システムの導入を考えている、またはすでにZoomを利用されている方におすすめです。対外的なウェビナー開催の場合はトラブル時に迅速な対応が求められるため、代理店を通した契約を検討するとよいでしょう。
たとえば、Zoomの法人契約代理店であるブイキューブでは問い合わせメールに対して「1両日以内の返信」を掲げています。ウェビナーの配信サポートもありますので、さらに詳しくZoomウェビナーについて知りたい方はこちらも合わせてご覧ください。
V-CUBE セミナー・Zoomウェビナーを用いたウェビナーの開催事例
本章では実際に「V-CUBE セミナー」と「Zoom ウェビナー」を導入した事例を3つご紹介します。
1)【V-CUBE セミナー】月2回「Liveネットセミナー」を開催:弥生株式会社
弥生株式会社は中小企業や個人事業主、起業家向けに、会計や販売管理などの業務ソフトウェアの開発・販売・サポートをしている会社です。
製品の購入を検討しているお客様に向けて無料体験セミナーを実施していたが、オフラインでのセミナーの開催は地域に制限があり、全国規模でお客様に製品の体験をしてもらうことができないという課題を持っていました。
V-CUBE セミナーを導入したことで、月に2回「Liveネットセミナー」と題してウェビナーを実施し、これまでアプローチできていなかった地域のお客様に対してのアプローチに成功し、全国規模での集客に繋がったとのことです。
2)【V-CUBE セミナー】オンラインセミナーを年間500コース以上配信:株式会社大塚商会
株式会社大塚商会はIT機器やソフトウェア、ソリューションの販売やサポートを幅広く手がけている会社です。
元々会場型の大規模なセミナーを実施していたが、会場費や集客のための宣伝費、セミナー運営のための人件費などのコストによってセミナーの実施回数に制限が生じてしまったり、地方での開催がコスト面や集客見込みの面から厳しく、地方の顧客に参加してもらいづらいという課題を持っていました。
V-CUBE セミナーを導入し、ウェビナーを実施したことで、自社のスタジオから配信が可能になり、セミナー実施にかかるコストを大幅に削減したことで、オンラインセミナーは年間500コース以上配信するなど実施回数の増加、以前まではできなかった地方の顧客の獲得に繋がったとのことです。
【Zoomウェビナー】CRMツールと連携:株式会社タービン・インタラクティブ

株式会社タービン・インタラクティブは、BtoBビジネスのマーケティングやブランディングに関するサービスを提供している会社です。
もともと、月に1〜2回ほどBtoB向けのウェビナーを開催していましたが、CRMツールなどと連携して参加者の動向を把握し、セミナーをより顧客にあったものにしたいと考えていました。また、参加者が使いやすく安定したツールを使って配信したいという課題も同時に抱えていました。
Zoomウェビナーを導入したことで、ウェビナーとCRMツールである「HubSpot」を連携させることができ、見込み客の開拓や顧客の育成をスムーズに行えるようになりました。また、PCだけでなくスマホ、タブレットなどの端末に対応している点やZoom独自の圧縮技術により配信中に音声や映像が途切れることが少ない安定性も評価されています。
ウェビナーを成功させるためのポイント

ウェビナーは場所による制約をなくすことで集客しやすくしたり、労力やコストを削ることができたりと様々なメリットがあります。
一方で、開催するにあたっていくつか注意なければならない点も存在します。
主な注意点は以下の4つです。
本章では上記の3つの注意点をそれぞれ詳しく解説していきます。
便利なウェビナーを成功できるように、注意点をしっかりと確認しておきましょう。
1.コンテンツの質を担保する
場所による制限がなく、参加しやすいウェビナーといっても、提供するコンテンツに魅力がなければ集客することは難しいでしょう。また、集客に成功したとしても、参加後の満足度が高くなければ、期待以上のリード獲得に結びつかないことも考えられます。
そのため提供するコンテンツの質を高くすることを常に考えなければなりません。
コンテンツの質を担保するには、セミナーを開催する目的・ターゲットをしっかりと定めることが重要です。例えばターゲットを「初心者向け」「上級者向け」などのように限定することで、参加対象者を絞り込むことができます。参加者を絞ることで、具体的にテーマを設定し、よりターゲットに寄り添った内容のコンテンツを提供できるため、ユーザー一人ひとりの満足度の向上につながります。
以下のようなウェビナーの目的に合わせて、ターゲットを絞りましょう。
- 新規顧客の獲得
- 既存顧客との関係強化
- 自社の社員教育
また、配信する映像や動画の質もコンテンツとして考えるうえでは非常に重要です。
画質や音声の質、ユーザーが内容を理解しやすいように字幕を付けるなどの工夫も、コンテンツの質に大きく関わってきます。常にユーザー目線に立って、配信する映像や動画自体のユーザビリティを高めることも忘れないようにしましょう。
弊社ブイキューブの提供している「Qumu」は配信する映像や動画をよりユーザビリティの高いものにする動画編集ツールを標準装備しています。
スライド連動のコンテンツを簡単に作成したり、字幕の挿入、トリミング、動画のカット・並べ替えなどを他のソフトウエアを使わずにQumuだけで完結させることが可能です。
出典:Qumu
「Qumu」についてさらに詳しく知りたい方はこちらをご確認ください。
2.身だしなみや言葉遣いには気をつける
ウェビナーでは映し出されるセミナー講師や開催側との距離が近く、参加者は表情や身だしなみをしっかりと見ることができるため、安心感を持ってもらいやすいです。
しかしそれが、かえって逆効果になることもあります。例えばオンラインでの開催だからと油断して、いつもよりラフな服装をしたり、ネクタイが歪んでいたりすると、参加者は普段からだらしない人なのだという印象を持ってしまいます。。スーツを着るなら、いつも以上にしわやネクタイのねじれにも気を付ける必要があるでしょう。。
オンライン上では、いつも以上に身だしなみや言葉遣いに気を付け、参加者が快くウェビナーを受けられるように務めましょう。。
3.音割れや騒音、映像の乱れなどがないようにする
オンライン上で開催するウェビナーでは、音割れや音声のずれ、映像の乱れが起こることがあります。インターネット環境が安定しない場合、リアルタイム配信中に映像や音声が途切れてしまうことも。
配信中のトラブルが不安な場合は、セミナー開催前に社内限定でテスト配信を実施してみるとよいでしょう。テスト配信を行うことで、事前にインターネット環境を確認でき、音割れや音声のずれのチェック、さらにはウェビナーを行う上で重要な資料共有などの機能もチェックできます。
もし映像が乱れたり音が途切れたりする場合は、インターネット環境が良くない可能性が高いです。より良いインターネット環境を用意するか、ルーターで補完してみてください。また、PCに内蔵されているタイプのカメラやマイクではなく、外付けの配信用カメラやノイズキャンセリング機能付きのマイク、話している人の音声のみを拾うピンマイクなどを導入することで、よりクリアな音声を届けられ、快適にウェビナーを開催できるでしょう。
4.参加者へリマインドする
ウェビナー参加者へ複数回案内を送りましょう。99firm社の調査でウェビナーの平均出席率は46%という数値が出ています。申し込んでも、半分以上の人が出席しない傾向があります。
一方、Peatixの調査では、集合型のイベントの出席率は85.7%という結果が出ているので、集合型のセミナーよりもウェビナーの方が出席率が低いという結果となっています。したがって、リマインドを行い、出席率を高めてもらう取り組みが必要です。
電話やメールでリマインドを行い、ウェビナーへのモチベーションを保たせる工夫をしましょう。電話であれば前日、メールであれば、前日と当日には必ず送りましょう。
メールの場合は、他のメールに埋もれてしまう場合もあります。開封確認ができるツールなどの導入して、未開封であれば電話などの他の手段でリマインドをするのもおすすめです。
また、ウェビナーの参加者はパソコンを使い慣れた人ばかりではありません。メールの文面で、開催日時だけでなく、ウェビナーシステムへの入室の仕方やチャットツールなどの使い方を丁寧に案内しましょう。また、ウェビナーはオンラインシステムを利用する以上、音声が流れなかったり、動画が映らなかったりするなどのトラブルが発生する可能性があります。
念のため、ウェビナーを開催する際はサポート体制があるシステムを使うようにしましょう。
まとめ|開催目的に合わせてセミナー開催方法を決定しよう
ウェビナー開催は、会場開催型のセミナーよりもメリットが多いと思われた方も多いのではないでしょうか。
実際にウェビナーでの開催を検討する場合には、以下のような観点から開催方法を決めてみましょう。
- どのくらい準備コスト、労力がかかるか
- 同テーマでの複数開催を予定しているか
- 全国各地でのセミナー開催を検討しているか
また、どのウェビナー製品を導入するか検討する際には、以下の項目で整理してみることをおすすめします。
- 機能やサポート面
- 参加人数の規模
- 1回あたりの開催費用
このようにセミナー開催の目的や集客規模に沿って検討を進めた結果、ウェビナー開催が合いそうだと判断した場合は、具体的にどのウェビナー製品を導入するか検討を進めてみてください。
はじめてのオンラインイベント開催ガイド

ウェビナーやオンライン説明会など、オンラインイベントを開催する際に必要な情報をまとめた資料です。ぜひお役立てください。
内容の一部をご紹介
- オンラインイベントを成功に導く事前準備ポイント
- 配信ツールの選び方
- プロが教える配信Tips