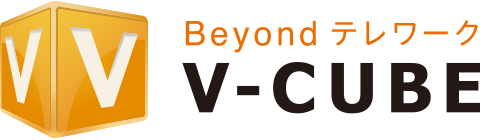インタビュー
空港施設やスポーツ施設など、国内外のさまざまな施設の建築設計を手がける総合設計事務所「梓設計」。情報システム部 部長/広報室室長 柴峯 一廣氏と情報システム部 主任 膳棚 敬一郎氏に、V-CUBE ミーティングを導入した経緯と効果についてお話しをお聞きしました。
6か所に7台の専用端末を設置。遠隔会議や社内研修などにV-CUBE ミーティングを活用
 「ほぼ毎日のペースで利用しており、年間トータルでみると400時間以上V-CUBE ミーティングを利用しています」 (柴峯氏)
「ほぼ毎日のペースで利用しており、年間トータルでみると400時間以上V-CUBE ミーティングを利用しています」 (柴峯氏)
梓設計では、V-CUBE ミーティングをどのように利用しているのか教えてください。
V-CUBE ミーティングの利用を開始したのは2009年になります。V-CUBE ミーティングの導入当初は、営業会議やデザインレビュー会議など、まさに「会議」の用途が多かったのですが、最近では本社・支社に講師を迎えて各拠点を接続した20~30名規模の社員研修に利用する機会なども増えています。頻度は少ないですが海外の現場との連絡に利用することもあります。
接続する拠点は決まっていますか。
基本的には、専用の端末を設置した拠点からV-CUBEを利用しています。端末を設置している拠点は本社のある東京都品川区 (2台)と、羽田設計室 (1台)、大阪支社 (1台)、九州支社(1台)、東北事務所 (1台)、名古屋事務所 (1台)の国内6拠点です。
海外ではどこの国で利用しているのでしょう。
案件ごとに場所は異なりますが、中国をはじめモンゴルやハンガリーなどでも利用したことがあります。
利用する頻度はどのくらいでしょうか。
正確には把握できていませんが、ほぼ毎日のペースで利用しており、年間トータルでみると400時間以上になると聞いています。
 V-CUBE ミーティングで4つの拠点を接続し、打ち合わせをする様子
V-CUBE ミーティングで4つの拠点を接続し、打ち合わせをする様子
週始めの定例会議などに必要な出張経費を削減するために遠隔会議システムを導入
V-CUBE ミーティングを導入した目的を教えてください。
V-CUBE ミーティングによるWeb会議システムを導入した一番の目的は、出張コストの削減です。特に定例の会議を開催するために、毎回、福岡や大阪などから担当者が本社に出張していましたので、それにかかる交通費や宿泊費といった経費を考えると、遠隔会議ができる環境を用意すれば大幅にコストを削減でき、またスケジュールの調整などもしやすくなると考えました。
これまでは要件に見合う遠隔会議システムが見つからなかった
遠隔会議システムを導入した経緯を教えてください。
情報システム部から提案をして導入を決定しました。
遠隔会議システムの導入に関しては、実は10年近く導入する機会を伺っていました。しかし、当社の要件に見合うシステムが見つからず、V-CUBE ミーティングなど使えそうなWeb会議システムが登場してきたことから、このタイミングで導入を本格的に検討することになりました。
システム選定要件とは、どのようなことだったのでしょうか。
遠隔会議システムの選定に関する要件は、次のとおりです。
- システムやPCに詳しくない社員でも、簡単に使えること
- 専用の端末がない場所からでも利用できること
- 導入が簡単にでき、運用コストがかからないこと
- 高画質で相手の表情などが確認できること
- 専用のネットワーク回線でなくても利用できること
スイッチを入れたらすぐに使え、
面倒な操作が不要なのがV-CUBE ミーティング最大の魅力
 「利用コストは定例の会議を1回開催するぐらいの費用負担で済みます」(膳棚氏)
「利用コストは定例の会議を1回開催するぐらいの費用負担で済みます」(膳棚氏)
V-CUBE ミーティングを選択した理由を教えてください。
導入するシステムを選定する際には、実際に試用した上で使い勝手や画質を確認しました。
PCのスイッチを入れたらすぐに使え、面倒な操作がいらないということ。さらには普段使い慣れたマウスで操作ができるので簡単に操作できるということが、V-CUBE ミーティングを選択した最大のポイントです。
また専用の機器などを導入しなくても、また専用のネットワーク回線などを増設しなくても、インターネットに接続できるPCがあればどこからでも利用できるという点も、当社の求める要件と合っていました。結果的に、使いやすさを考え各拠点には専用の端末を設置していますが、必要に応じて海外の現場などからも利用できるのでとても便利です。
コストも定例の会議を1回開催するぐらいの費用負担で済み、サポートも丁寧で、市場シェアが高い製品なので、安心して利用できるということも評価ポイントになりました。
手軽に社員研修を開催できるようになり、会社のレベルアップにもつながっている
V-CUBE ミーティングを導入した効果を教えてください。
コスト削減に関しては、1回の定例の会議にかかっていた経費だけを考えても導入前の1/4ぐらいになっています。通常の会議でも、これまでは電話やメールでしか話ができなかった相手とも、顔を見ながら打ち合わせができるようになり、表情や顔の色が見えることで、相手の様子がリアルにわかり、会議の密度が高まったという声も聞かれます。
また、V-CUBE ミーティングの導入後に社員研修をする機会が急増したという話しをしましたが、その多くは、「建築士法第22条」(建築士は必要な知識と技能の維持向上に努めなければならない)というCPD制度に対応した研修になります。
V-CUBE ミーティングの導入以前は、現在のように研修を手軽に実施するのはできませんでした。V-CUBE ミーティングを利用すれば各拠点に講師を派遣したり、また各拠点から本社に集合したりしなくても研修が実施できるということがわかりましたので、研修を開催する回数は増えています。これもV-CUBE ミーティングを導入した大きな効果であり、技術者の、ひいては会社のレベルアップにつながっていると考えています。
今後の拡張予定とV-CUBEへの期待
今後の拡張予定などあれば教えてください。
V-CUBE ミーティングを使って開催した研修の動画をアーカイブで保存しておいて、あとから見られるようになれば便利だと思っており、アーカイブオプションの導入を検討する余地はあるかと思っています。
V-CUBEへの期待などあればお聞かせください。
V-CUBE ミーティングの導入後に、他社よりシステムの入れ替えを提案されたこともあったのですが、使い勝手の部分でV-CUBE ミーティングに劣るところがあり、採用には至りませんでした。V-CUBE ミーティングに対しては、現状でも満足度はとても高いのですが、さらに画面構成を決められたパターンだけでなく自由に操作ができ、資料のアニメーションなど、画面上での動きも共有できるようになれば、さらに利用頻度は上がるかと思います。期待していますので、今後ともよろしくお願いいたします。
※取材日時 2012年7月
※記載の担当部署は、取材時の組織名です。